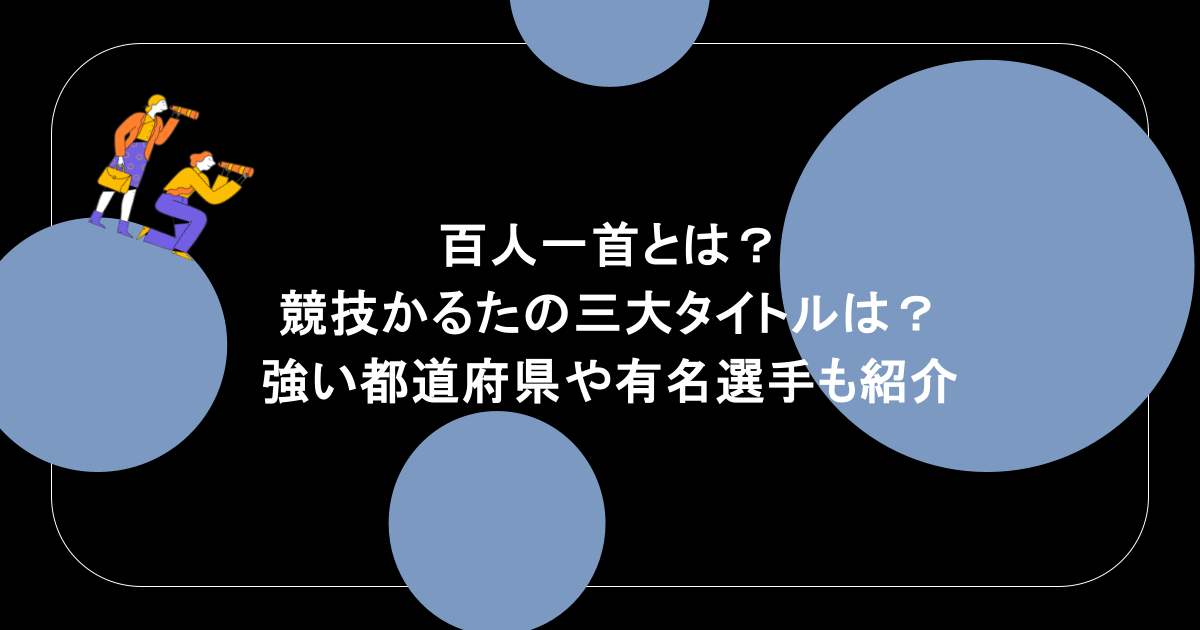今では世界中で親しまれているカードゲームですが、そのルーツは9世紀ごろの中国にあると言われています。
当時は、紙に絵を描いて遊ぶ「葉子戯(ようしぎ)」という遊びが始まりとされており、これがシルクロードを通って中東、さらにヨーロッパへと広がっていったそうです。
また、印刷技術が発達したことで、カードゲームは庶民の間にも広がり、国ごとに個性豊かなゲームやデザインが生まれていきました。日本には16世紀ごろにポルトガルからカードが伝わり、その後は「花札」や「百人一首」など、独自の和風カード文化へと発展していきました。
トランプの歴史
トランプはイスラム世界を経由して中東に広まり、13世紀にはマムルーク朝(現在のエジプト周辺)で使われていた豪華な装飾のカードも見つかっています。
このマムルーク・カードには、剣・棒・カップ・コインといったマーク(スート)が描かれており、現在のトランプにもその影響が見られます。
ヨーロッパには14世紀ごろに伝わり、イタリアやスペインを経て、最終的にフランスで現在おなじみの「スペード・ハート・ダイヤ・クラブ」というデザインが確立されました。
印刷技術の進歩とともにこのデザインが普及し、今では世界中で使われる標準的なトランプのスタイルとなっています。
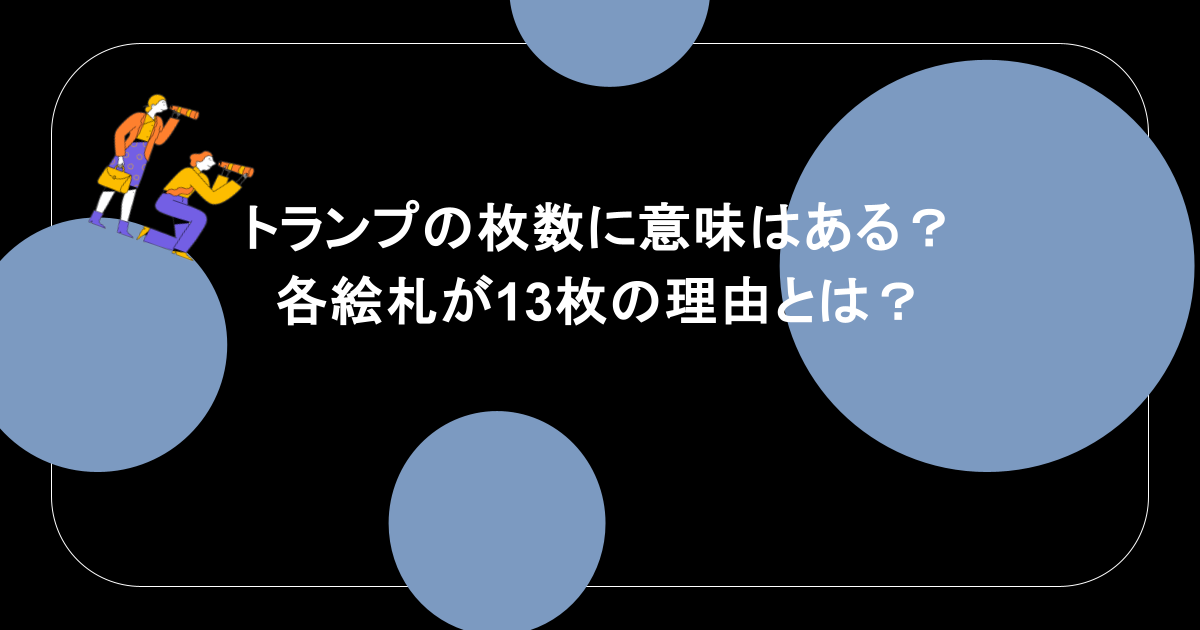
花札の歴史
「花札(はなふだ)」は日本発祥のカードゲームと思われがちですが、実はポルトガルから伝わった「カルタ(Carta)」がそのルーツとされています。16世紀ごろにトランプの原型が日本に伝わり、そこから日本独自の進化を遂げて生まれたのが花札です。
江戸時代にはギャンブルの道具として人気を集めましたが、幕府による取り締まりが厳しくなる中で、何度もデザインを変えながら生き残ってきたそうです。
現在のような「12か月」「四季の草花」をテーマにした絵柄は、明治時代ごろに定着したといわれています。
代表的な遊び方には「こいこい」や「花合わせ」などがあり、今でも根強いファンが多く存在します。
一見レトロに見える花札ですが、実は日本の文化と歴史が詰まった、奥深いカードゲームなのです。
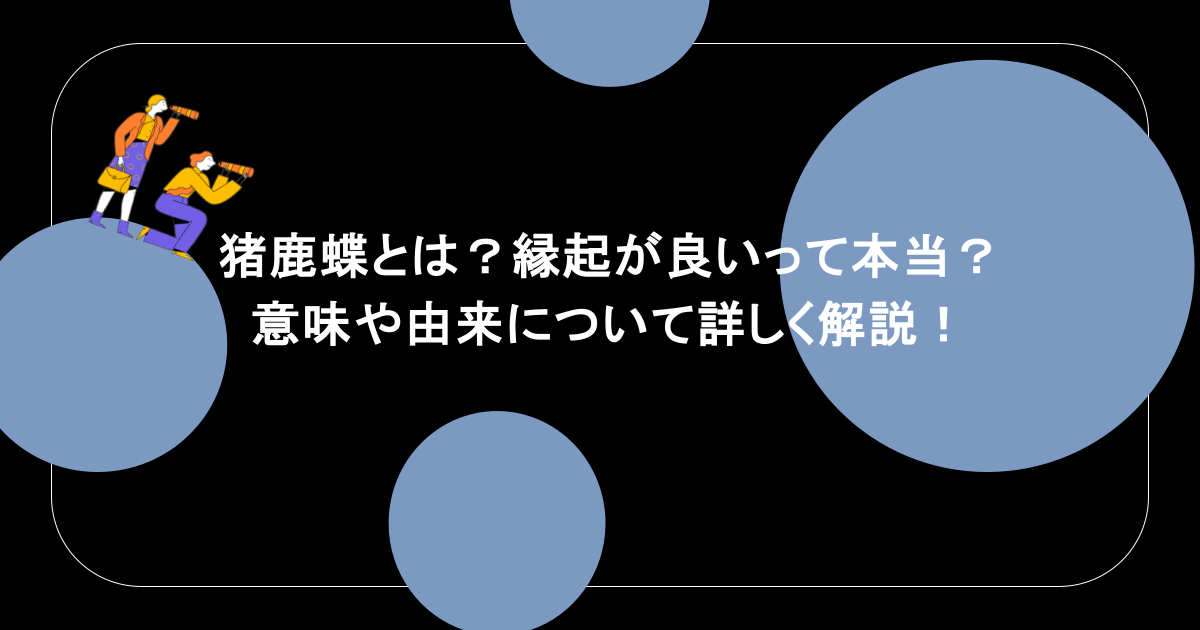
百人一首の歴史
「百人一首(ひゃくにんいっしゅ)」は、100人の歌人が詠んだ和歌を1首ずつ集めた、日本の古典文学の傑作です。
もともとは、鎌倉時代の歌人・藤原定家(ふじわらのさだいえ)が、京都・嵯峨野にある山荘「小倉山荘」のふすまを飾るために選んだことが始まりとされています。このため、正式には「小倉百人一首」と呼ばれることもあります。
百人一首は、貴族たちの教養や遊びの一環として親しまれ、やがて「かるた遊び」として庶民にも広がっていき、江戸時代には木版印刷によって広く普及し、正月の風物詩としても定着していきます。
百人一首の魅力は、短い31文字の中に、恋や季節、人生の機微が美しく詠まれていること。現代でも「競技かるた」として全国大会が開かれたり、アニメや漫画でも取り上げられたりと、長い年月を経ても多くの人に愛され続けています。