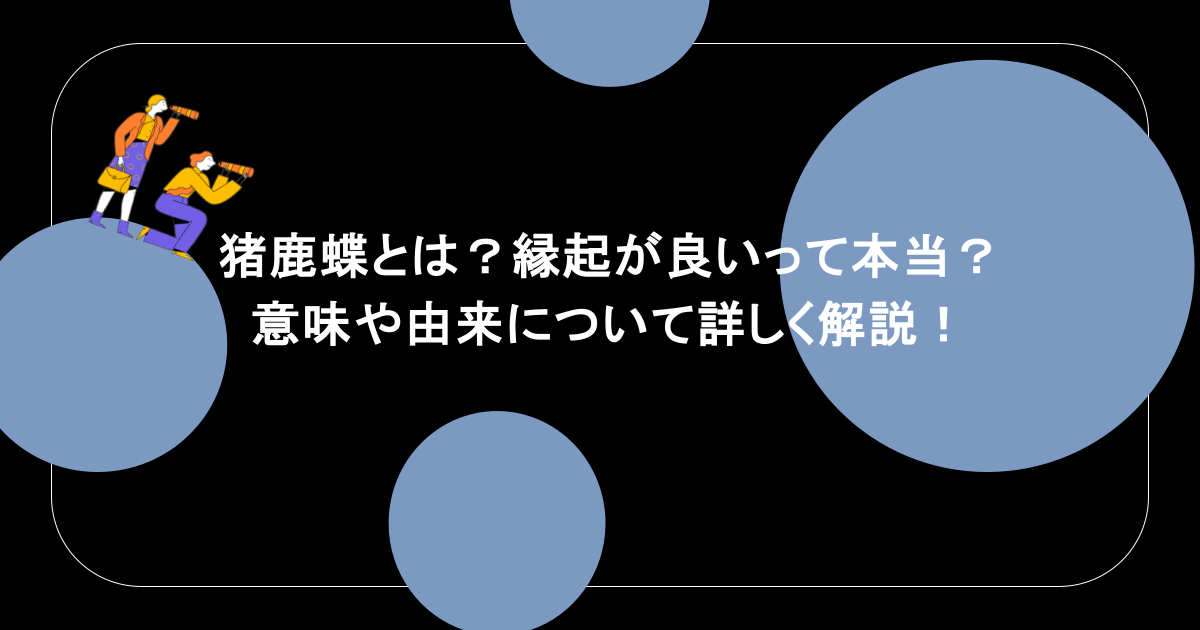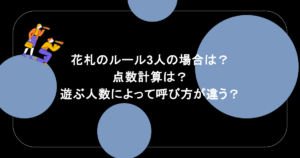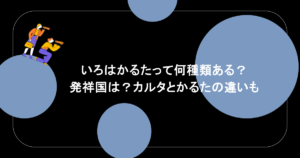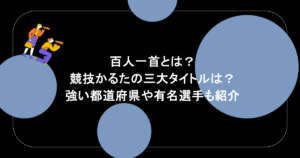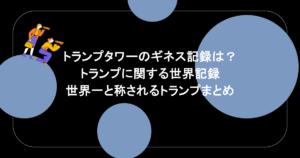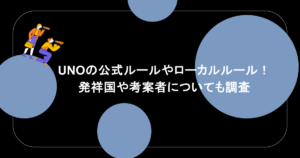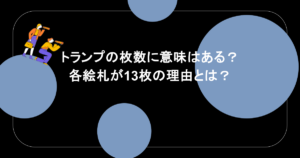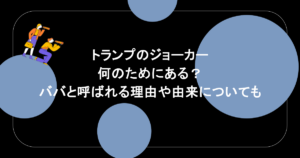みなさんも「猪鹿蝶」という言葉をどこかで耳にした経験があるかもしれません。この猪鹿蝶とは日本の伝統的なカードゲームの花札で使われる役の名称で、もっとも有名な役のひとつと言っても過言ではないでしょう。実はこの「猪鹿蝶」という言葉は、縁起がいいとされています。
そこで今回は猪鹿蝶とはどのような言葉なのか意味や由来など、さらには縁起が良いと言われる理由について詳しくご紹介していきます。
猪鹿蝶とは?
猪鹿蝶とは「いのしかちょう」と読み、花札で使用される役の名称です。これは花札で猪、鹿、蝶が描かれた札を3枚揃えた際に加点される役で、花札でよく遊ぶ人ならばお馴染みだと思います。
花札では、1月〜12月まで月毎にそれぞれ4枚ずつ札があり、その中で猪、鹿、蝶は以下の3枚が該当します。
- 7月の「萩に猪(はぎにいのしし)」
- 10月の「紅葉に鹿(もみじにしか)」
- 6月の「牡丹に蝶(ぼたんにちょう)」
これらはそれぞれ10点札と呼ばれ、3枚全て揃えることで「猪鹿蝶」という役が完成するというわけです。
猪鹿蝶の由来はなに?
次に猪鹿蝶の由来についてご紹介します。実は猪鹿蝶は、花札に描かれている植物と動物の関係性に由来しており、「萩に猪」「紅葉に鹿」「牡丹に蝶」のそれぞれに独自の由来が存在しています。
萩と猪
萩(はぎ)とはマメ科の植物で、古くから日本では萩の花は猪が横たわる場所という意味の「伏猪の床(ふすいのとこ)」として認識されていました。
普段は凶暴で野性的な猪ですが、美しくて優雅な萩の花の前ではゆっくりと体を休めると言われています。
このことから、美しい萩と野性的な猪を対照的なもの同士の組み合わせが、日本の伝統的な絵画のモチーフとして古くから好まれてきたという歴史があります。
紅葉に鹿
紅葉と鹿の由来にはいくつか説があるようですが、中には少し悲しい物語が関係しているものもあります。
昔、お堂で習字の練習をしていた少年が紙を食べようとしていた鹿を見つけ、追い払おうと文鎮を投げたところ、それが鹿の急所に当たってしまい鹿が死んでしまいました。
その当時、鹿は”神の遣い”と考えられており、神聖な存在として人々に崇められていました。そのため鹿を殺してしまった少年は非常に重い罪に問われ、生き埋めの処罰を受けてしまいます。
このことに心を痛めた少年の母親は、少年の安息を願ってもみじの木を植えたことが「紅葉に鹿」の由来だとされています。
他の説では、「鹿は秋の季語であり、鹿=紅葉を連想させる言葉」や「肉食が禁止されていた江戸時代、鹿肉のことを”もみじ”と呼んでいた」などの由来の説もあるようです。
牡丹に蝶
牡丹は非常に華やかで美しい花として知られており、あの世界三大美女の一人にも名を連ねる楊貴妃も牡丹に例えられたほど、数ある花の中でも「美」を象徴する存在です。
また、蝶は古くから魂や復活を象徴する生き物として認識され、ギリシャや古代ローマの彫刻にも描かれています。さらに日本では「蝶=長」に通ずることから「長寿」を象徴する生き物だとも言われており、非常に縁起が良いものとされています。
「美」を象徴する牡丹と、「長寿」を象徴する蝶のどちらも縁起が良いもの同士を合わせたものが「牡丹に蝶」の由来ではないかと考えられているようです。
猪鹿蝶は縁起が良いって本当?
猪鹿蝶とは花札の中でも点数が高い役なので、花札好きにとっては良いイメージのある言葉かもしれません。また、「猪鹿蝶」という言葉は非常に縁起が良いともいわれており、猪、鹿、蝶のそれぞれに特別な意味があります。よく花札 意味 怖いとも言われることもありますが、実は多くの札が縁起が良いものとされています。
ここでは猪鹿蝶が縁起が良いとされている理由についてみていきましょう。
猪 = 子孫繁栄
猪は畑を荒らす害獣として知られており、非常に凶暴で危ない動物とも言われます。しかしそんな猪は実は多産な動物で、1回の出産で6〜12匹ほどの子供を産みます。そのことから猪は、子孫繁栄を象徴する動物として縁起が良いとされているようです。
また猪突猛進という言葉があるように、目標に向かって障害を乗り越える力強さの象徴とも考えられており、これから何かを始めようとしている人にとってはピッタリの動物ともいえるでしょう。
鹿 = 金運・財運
鹿は長寿や幸福の象徴とされることも多いですが、風水の世界では鹿は財をもたらす動物とされ、金運や財運が向上すると考えられています。これは、「鹿」の中国語が「給料」と同じ発音であるためで、その他にも鹿のツノや鹿の置物などが風水では富を呼び込む力があると信じられていることも関係しています。
また、鹿は群れで生活する動物のため、社会的な調和や平和の象徴ともされているため鹿は非常に縁起の良い動物と言えます。
蝶 = 長寿・復活
最後に蝶ですが、こちらは先のご紹介していたように「蝶=長」に通ずることから「長寿」を象徴する生き物だとも言われています。また、蝶は幼虫からサナギを経て美しい蝶へ成長(変体)することから、魂の不死や再生、復活などの意味もあり、輪廻転生や変化といった縁起の良い象徴です。
さらに蝶は、人の血液を吸う厄介者の「蚊」や汚れた場所などに住み着くイメージのある「ハエ」などとは全く異なり、春には美しい花々の周りを優雅に飛び回る姿から風水では「喜び」や「自由」といったポジティブなパワーをもたらしてくれる生き物だと信じられています。
まとめ
猪鹿蝶とは日本の伝統的なカードゲームの花札で使われる役の名称として知られており、「萩に猪」「紅葉に鹿」「牡丹に蝶」の3枚で構成され、花札が好きな人にはおなじみの言葉です。
この花札で使用されている札にはそれぞれ意味や由来が存在しますが、実はこの猪鹿蝶という言葉は縁起が良いとされており、猪、鹿、蝶それぞれに子孫繁栄や金運、長寿などの意味があり、この3つがひとつに結び付いた「猪鹿蝶」という言葉はとても強い幸運の象徴ともいえるのではないでしょうか。
花札で遊ぶ機会があった際には、猪鹿蝶などの札や役の意味を知ったうえで遊ぶことで、より一層楽しめること間違いなしです。