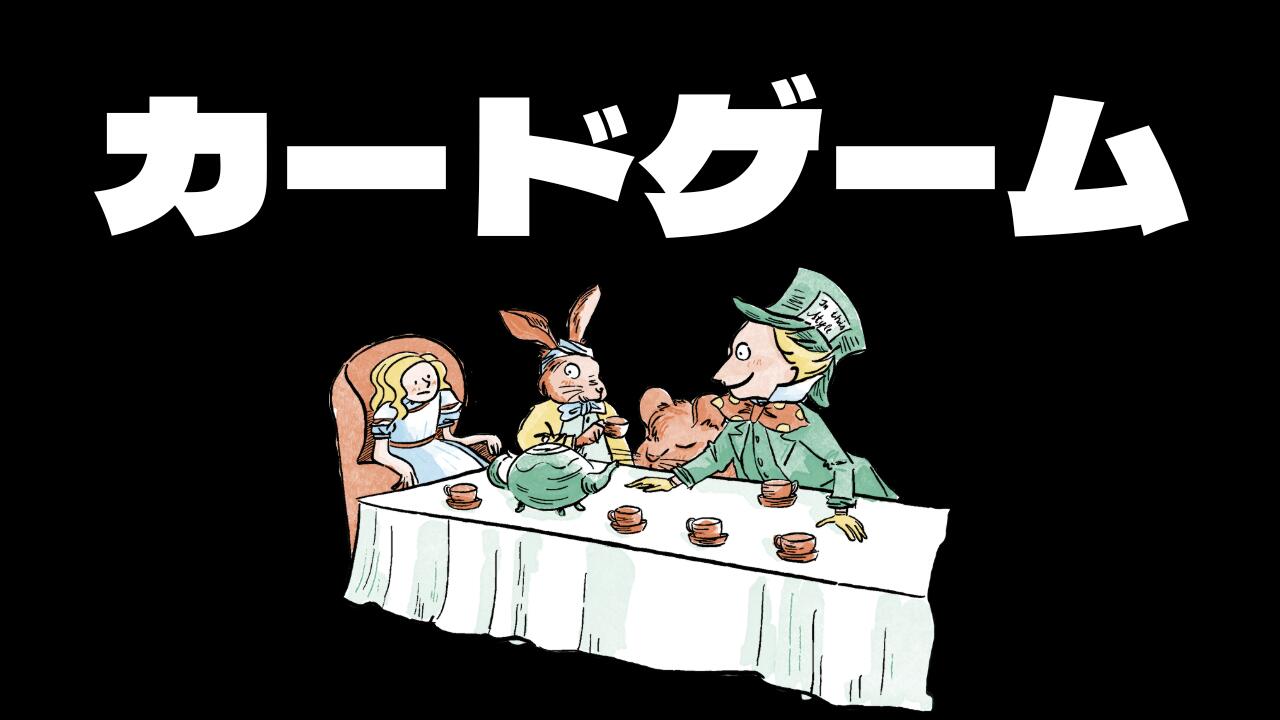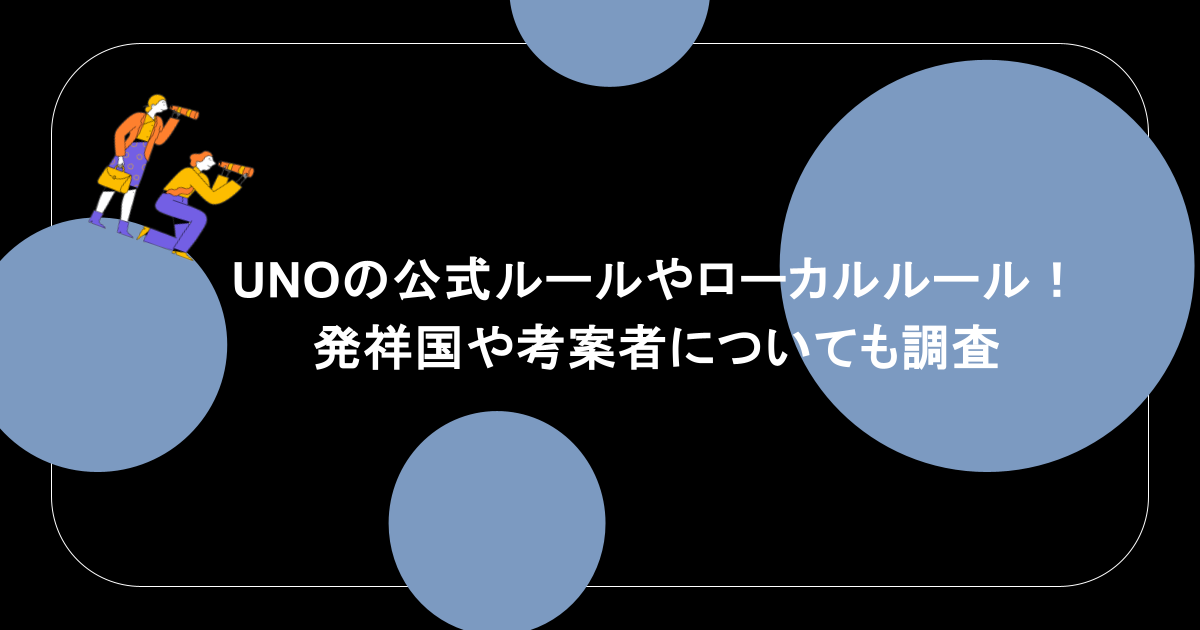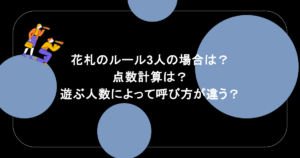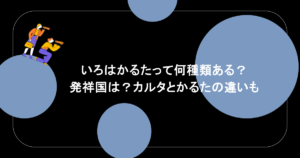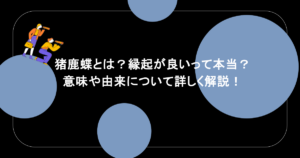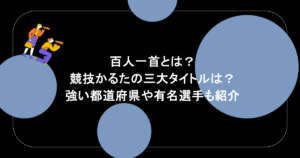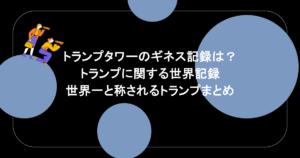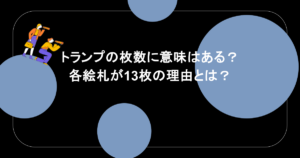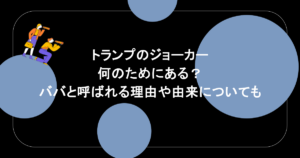旅行などのお供に最適、世界中で愛されている人気カードゲーム「UNO」。実は公式ルールではあまり遊ばれていないのですが、公式ルールで遊ぶのも楽しいんですよ!
今回はUNOの公式ルールやローカルルール、発祥国や考案者などの情報について紹介します。
UNOの公式ルール
では早速UNOの公式ルールについて紹介しますよ。まず、UNOの公式ルールの重要なポイントですが、公式ルールにおけるUNOは複数回ゲームを行い順位を決めるゲームなんです。また、一回一回のゲームにおいて最後の一人が残るまでゲームを続けるということはなく、最初の一人が上がった瞬間そのゲームは終了、次のゲームに移ることになりますよ。では、総合的な順位はどのように決定するのでしょうか。
出典:オモコロチャンネル
順位は点数で決定
公式ルールにおけるUNOの順位は、点数によって決まります。この点数は各カードに定められており、数字のカードはその数字分の点数(9なら9点、0なら0点です)、スキップとドロー2、リバースは20点、ワイルドとワイルドドロー4は50点分の点数になります。高い点数のカードを手札に残したまま他の誰かに上がられると不利になってしまうので、強力なワイルドドロー4などを温存するのかそれとも早めに出しておくのかといった戦略性がありますよ。
公式ルールにも二通り?
点数の計算方法については、国際ルールと日本ルールの2つがあるのですが、現在は日本ルールが使われることは少ないようです。
国際ルールでは、誰か一人が上がった時点で残りのプレイヤーはそれぞれ自身の手札として残ったカードの点数を計算、それぞれの点数が全て上がったプレイヤーの点数に加算されます。これを繰り返してプレイヤーの誰かが500点を先取すると優勝になります。敗者は各ゲームで一律0点なため、ゲーム毎に勝者が頻繁に変わるような展開だとかなり長丁場になりますね。
日本ルールでは
ちなみに日本ルールでは、500点先取ではなく5ラウンドの回数制とされています。点数のルールも少し違い、上がったプレイヤーが他のプレイヤーの手札分の点数を貰うことができるのは同じなのですが、日本ルールでは更に負けた各プレイヤーが自身の点数分点数を減らされてしまうのです。このルールのため、500点先取はより遠くなってしまうというのも、5ラウンド制の理由なのかもしれません。
その他の公式ルール
他に抑えておきたい公式ルールとしては、最初の手札は7枚である点、一度に出せるカードの枚数は1枚だけな点、前のプレイヤーがドロー2やドロー4を出してきた時、自分もそれらのカードを出して次のプレイヤーに流すというのは出来ないということなどがあります。
出せるカードが手札にない時はカードを一枚引きますが、この時引いたカードを出せる場合そのまま出していい、というのは公式ルールでもそうですよ。なお、出せるカードがあっても一枚引くことは可能、ただ一枚引いた後にそれとは別のカードを出すというのはできません。
特殊カードが一枚目に出た時は?
各ゲームのスタート時に最初にめくったカードが特殊カードだった場合も、基本的にそのカードの効果は発動します。スキップが出たら最初に出すはずだった人は飛ばされますし、ドロー2なら最初に出すはずだった人はいきなり2枚引かされます。リバースだったら当初の予定とは反対方向でゲームをスタートし、ワイルドカードなら最初に出す人が色を自由に指定して始められます。
ただ、いきなりドロー4が出た時だけは、そのカードを山札に戻して新たに最初の一枚を引きます。いきなり4枚ドロースタートはあまりにもひどいですからね。
UNOのローカルルール
ここまではUNOの公式ルールを紹介してきましたが、ここからはUNOのローカルルールについて紹介します。まず、点数制にせずに一戦一戦勝負するというのもローカルルールと言えるでしょう。最後の一人が残るまでゲームを続けるというルールで遊んでいる人は多いのではないでしょうか。
また、いわゆる「禁止上がり」も公式ルールには存在しないローカルルールです。特殊カードで上がっちゃ駄目、というやつですね。公式ルールでは特殊カードは高い点数を設定されており、それらを最後の一枚に残すのもリスクがあるので禁止上がりは採用されていないのでしょう。
特殊カードに関するローカルルール
ドロー2やドロー4に同じカードを重ねてかわすというのも有名なローカルルール。たまりにたまって20枚ぐらい引かされた経験がある人もいるのではないでしょうか。重ねられるカードの範囲に関しては、「ドロー4を出したプレイヤーが宣言した色のドロー2を次のプレイヤーが持っていれば重ねられる」としたり、細かい差異がありますよね。
同じカードは複数重ねて出せるというローカルルールもあり、特に特殊カードの場合は、スキップを重ねて出した枚数分プレイヤーを飛ばすパターンとスキップをその回数繰り返すパターンがあったり、リバースを二枚出したら順番が入れ替わらなかったりなどのルールがあります。
公式版に収録されている新しい特殊カード
近年のUNOには、公式版にも「シャッフルワイルドカード」などの特殊カードが入っています。このカードに馴染みがない人もいるのではないでしょうか。シャッフルワイルドカードにも40点と点数が定められており、公式ルールの枠組みの中にあるようなのですが、同カードを使わずに遊ぶ人も多いというのが現状です。実質的に、シャッフルワイルドカードはローカルルール的な扱いになっていますね。
UNOの発祥国や考案者は?
UNOはアメリカ発のゲームです。1971年にアメリカ合衆国オハイオ州で理髪店を営むメリル・ロビンズさんが考案しましたよ。メリル・ロビンズさんは家族や友人と楽しむために新しいカードゲームを探していた際に、Craze Eightsというゲームにインスピレーションを受けてUNOを生み出したそうです。一個人が生み出したゲームが50年以上にわたって愛され続け、世界中の人が遊んでいるというのは凄い話ですね。
後発ゲームも誕生!
2018年にはUNOの兄弟作として「DOS」が登場。別ゲームとだけあってUNOとDOSの違いは結構あり、「UNO」が1を意味する言葉なのに対し「DOS」は2を意味する言葉ということで、DOSは「2」を意識した様々なルールが設定されています。UNOが好きな方は、一度DOSも遊んでみてはいかがでしょうか。
最後に
今回はUNOの公式ルールやローカルルール、発祥国や考案者について紹介しました。戦略性が高い公式ルールは面白いのですが、やはり時間がかかるのがネック。公式ルールを参考に、目標ポイントを減らすなどアレンジしながら遊ぶのもいいですね。