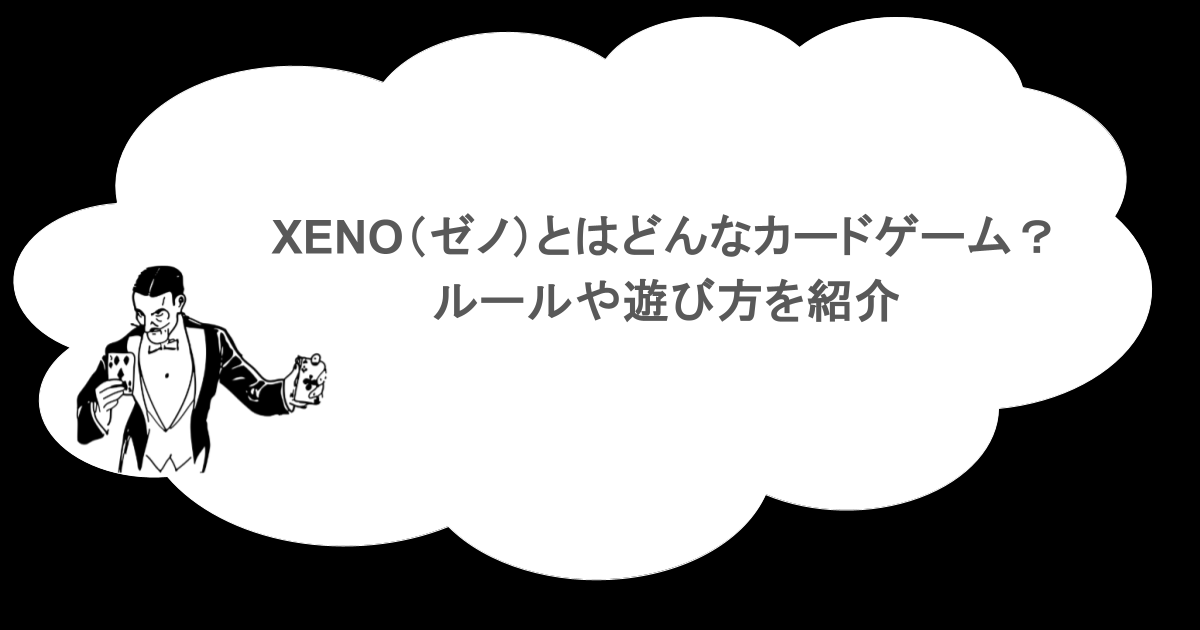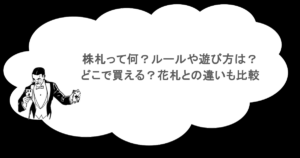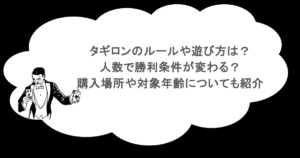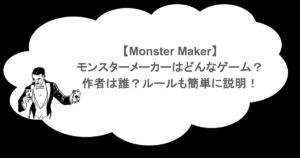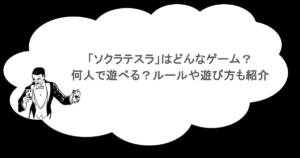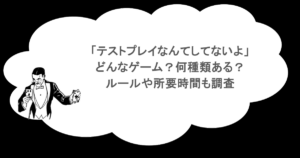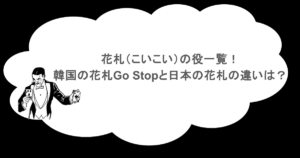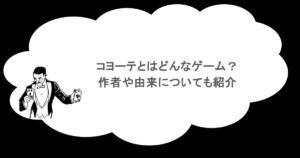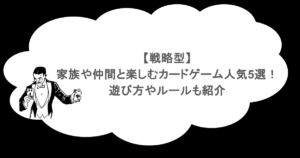カードゲームの面白いところは、意外な文化や流行から誕生することがある点で、巷で流行しているXENOもその一つです。そこでこの記事では、XENOというカードゲームを知らない人に向けた遊び方を紹介しています。簡単なルールなので、カードゲームはトランプしかやったことないという人でも手軽に始められると思うのでぜひ御覧になってください。
魅惑のカードゲームXENOの正体とは
XENOというカードゲームは、ラブレターというカードゲームを元にお笑い芸人だった中田敦彦が開発したゲームです。元となったラブレターは、2012年5月にデザイナーのカナイセイジが同人ゲームとして開発販売しており、あまりの人気から2022年には10周年を迎える快挙を成し遂げました。基本的なゲームの遊び方は、2枚の手札から1枚を場に出し、カードに書かれた効果を処理しながらゲームを進めていき、最終的に手札に一番強いカードを持っていた人が勝ちというルールです。
このルールに戦略的な要素を追加したのがXENOというカードゲームで、ラブレターの作者であるカナイセイジ公認の元中田敦彦が開発した経緯があります。
XENOのルールを理解してみよう
XENOというカードゲームはプレイ可能人数が2人から4人までとなっています。ゲームを開始する前に18枚ある山札をよく混ぜ、プレイヤー1人に1枚ずつ手札を裏向きにして配ります。次に転生札として、非公開のカードをプレイヤー1人ずつに配布します。この時手札のカードは他のプレイヤーに見られないように自分で確認することができますが、転生札は見ることができません。
次にじゃんけんやサイコロなどで順番を決めて、最初の人から順番に山札を引いてから手札を場に出すという作業を繰り返します。手札からカードを場に出したら、カードに書かれた効果を処理して、次の人に順番を渡していきます。これを山札が無くなるかプレイヤーが最後の1人になるまで脱落するまで繰り返します。
ゲームの勝敗の決め方とは
勝敗は山札のカードが無くなったときに、手札のカードに書かれた数字の合計を脱落者以外で競うか、他のプレイヤー全員を脱落させることで決まります。つまりXENOというカードゲームはカードの効果を理解し、いつそのカードを場に出すかが勝敗の鍵となっています。
少年:革命のカードについて
少年:革命はXENOのカードゲームで使うカードの種類で、強さが1で18枚中2枚存在します。少年:革命のカードは1枚使っても何も効果が発生しませんが、既に場に少年:革命のカードが1枚出ているときに使うと、プレイヤーを1人指定して、指定されたプレイヤーは山札から1枚引き、指定したプレイヤーが選んだ手札を捨てなければなりません。つまり、手札に強力なカードがありそうなプレイヤーの戦略を乱せるカードとなっています。
注意点は山札が無くなった順番に使っても効果を発揮することはなく、カードの効果で捨てさせられたカードの効果を発揮することがない点です。
兵士:捜査のカードを使ってみよう
XENOのカードゲームにある兵士:捜査は、カードの強さが2で全山札中2枚存在します。使った場合プレイヤー1人とカードの種類を1つ選択することができ、カードの種類を見事と当てたときは、当てられたプレイヤーが脱落します。ただし、当てられたプレイヤーが英雄のカードを持っていた場合は脱落させることができません。さらに当てられたプレイヤーは持っている手札を、全て効果を発揮しないまま捨て、転生札として配られたカードを手札にして、ゲームを続けます。
占い師:透視のカードを使いこなせ!
XENOのカードゲームにある占い師:透視のカードは、使うと指定したプレイヤー1人の手札を見ることができます。相手の戦略を見る利点がありますが、少年や兵士のような攻撃力のあるカードではないところが欠点です。しかし、カードの強さが3あるので、後半にゲームが膠着するような展開のときに持っておくとカードの強さでそのまま勝てる可能性のあるカードです。
乙女:守護のカードとは
XENOのカードゲームで使われている乙女:守護は、使うと次の自分の順番になるまで他のカードの影響を受けなくなる効果を持っています。カードの強さも4と高く、兵士や少年のカード効果を受けなくなるので、自分が攻撃できるような手札を持っていないときに使っておくと良いでしょう。ちなみに山札内に2枚存在するので、自分が乙女:守護のカードを持っていても、相手が効果を無効化してくる可能性がある点に注意しましょう。
死神:疫病のカード効果を紹介
死神:疫病とはXENOのカードゲームで使うカードのことで、使うと指定したプレイヤーに山札から1枚カードを引かせます。その後シャッフルさせた後に死神:疫病を使ったプレイヤーがシャッフルしたカードの中から裏向きで1枚を選択し、選んだカードを効果を発揮せずに捨てさせます。ただし、選んだカードが英雄のカードだった場合は転生の効果を発動するので、空振りになる場合があります。
貴族:対決のカードで相手を脱落させよう
貴族:対決のカードは、XENOのカードゲームにおいて使用すると指定したプレイヤーと手札の強さの数値で対決することができます。負けたプレイヤーは脱落してしまいますが、見せたカードが同じ強さだったときは対決したプレイヤーの双方が脱落するので、使うタイミングは慎重に見極めたほうがいいでしょう。
賢者:選択のカードで打開策を探そう
賢者:のカードは、XENOのカードゲームで使うと次の順番で山札からカードを3枚引き、その中から1枚を手札に加えることができる手札効果のカードです。遊戯王のオフィシャルカードにもある天使の施しと同じような効果というと分かりやすいかもしれません。
精霊:交換のカードを使ってみよう
XENOのカードゲームにある精霊:交換のカードは、指定したプレイヤーと自分の手札を交換するカードです。手札が悪いときに使うカードですが、できれば占い師:透視のカードを使った後にして後の展開を有利に進めたいところですね。逆に交換したくないときは、カードの強さが8あるので、そのまま山札を消費して終局させるのも一つの方法です。
皇帝:公開処刑のカードとは
皇帝:公開処刑のカードは、死神と同じく山札を指定したプレイヤーに引かせて、自分が指定したカードを捨てさせるカードです。ただし、死神は指定するプレイヤーのみに手札が公開されますが、皇帝は場の全てのプレイヤーに手札が公開される利点があります。また、英雄を公開処刑した場合はそのままそのプレイヤーが脱落になるので、ゲームを終わらせるカードと言っても過言ではないでしょう。
英雄:潜伏・転生のカードについて
英雄:潜伏・転生のカードは、XENOのカードにおいて唯一自ら使うことのできないカードとして存在しています。つまりこのカードは兵士や少年のカード効果で捨てさせられることがないと効果を発揮しません。カードの効果はカードを捨てさせる効果が英雄を持っているプレイヤーに対して行われ、指定された場合に限り転生の効果を発動することができます。転生とは脱落せずに転生札を手札にしてゲームを続けられる効果のことで、1回だけ脱落を防ぐことができるカードという認識が正しいでしょう。
まとめ
XENOのカードゲームは、元お笑い芸人だった中田敦彦がラブレターというカードゲームを元に開発したゲームです。ラブレターよりもゲームに戦略性が生まれ、より心理戦を楽しめるようになっているので、ボードゲームやカードゲーム好きの人から高く評価されています。また、ルールも簡単で覚えるカードの種類も少ないので、気になった方はぜひ一度遊んでみてください。